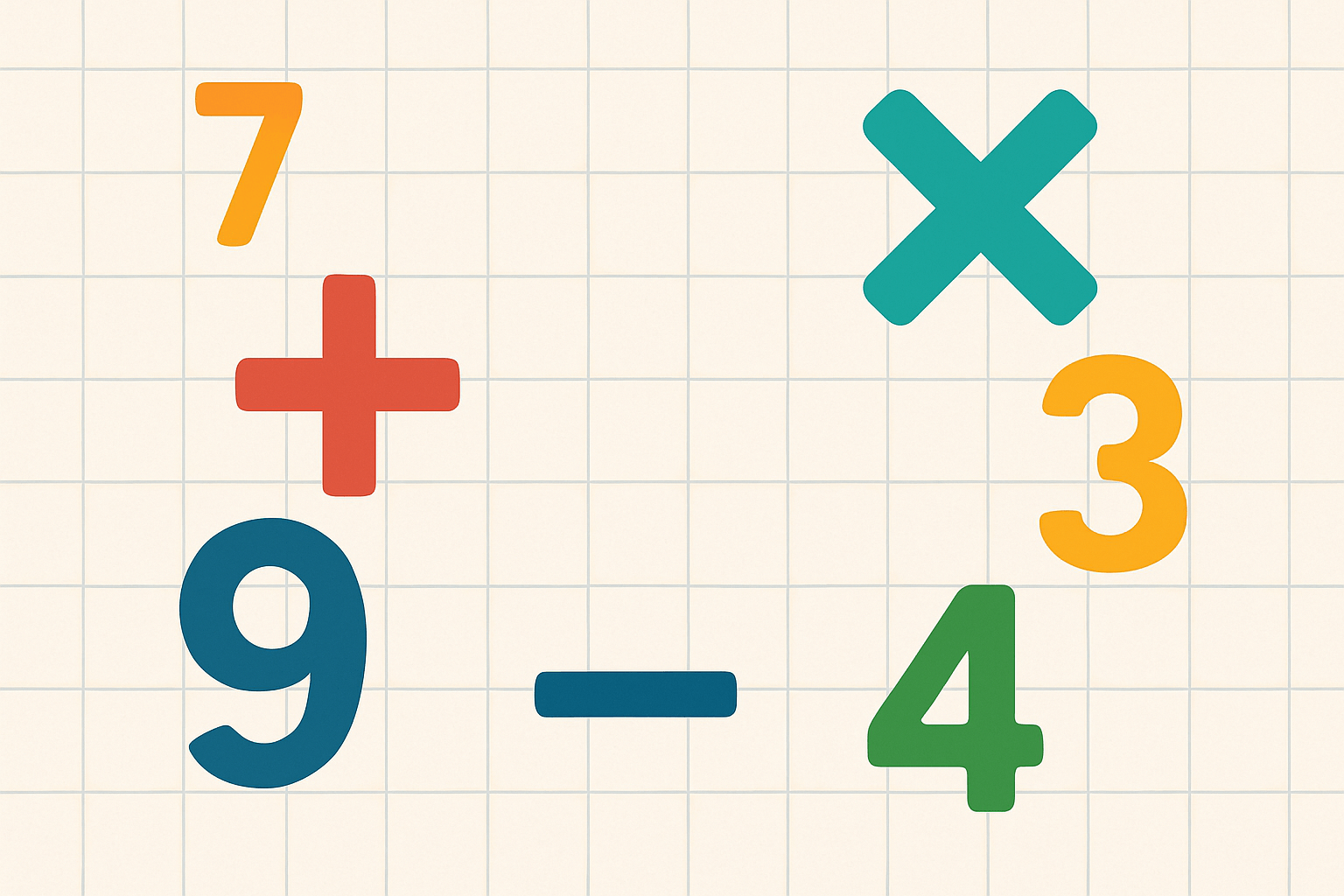脳内電卓の秘密を探る
「頭の中でパッと答えが出せる人」――あなたの周りにもそんな人、いませんか?
店員さんがレジを打つ前に合計を出したり、割り勘で電卓より先に金額を言い出したり……。
いわゆる“暗算ができる人”です。
彼らはいったいどうやってそんなスピードで計算しているのか?
そして、その脳の中はどうなっているのか?
この記事では、暗算が得意な人たちの“頭の中”を科学・心理・スキルの3方向から掘り下げてみます。
そもそも暗算は「才能」なのか?
結論から言えば、一部は才能、ほとんどはトレーニングです。
実際、暗算が得意な人の多くは、何らかの計算習慣を持っています。
- そろばん経験者
- 数字に対する“イメージ記憶”がある
- 子どもの頃から買い物や割り算を頭でしていた
- 単純に数字が好き
暗算力は「脳の特定の領域が発達しているから」と思われがちですが、
実際は「どう処理するかの戦略」にこそ秘密があります。
脳のどこを使っているのか?
暗算時に活動が活発になるのは、主に次の3つの領域です。
① 前頭前野(ワーキングメモリ)
- 複数の数字を一時的に記憶し、順序立てて操作する領域
- 「13×17=?」など、複数ステップがある計算で活躍
② 角回(かくかい)= 言語・数値変換の中枢
- 数を「言葉」として捉える、算数的思考の核
- 計算の公式や九九を思い出すときに使われる
③ 頭頂葉(とうちょうよう)
- 数量の概念や、数のイメージを空間的に捉える領域
- 暗算得意な人は「数を並べたビジュアル」をここで処理している可能性が高い
MRIによる研究では、熟練の暗算者ほどこれらの領域の同時活性が効率的であることがわかっています。
数字は「映像」で見てる!?驚きの暗算イメージ術
暗算が得意な人は、数字を“音”でも“式”でもなく“映像”として記憶していることがよくあります。
たとえば:
- 「27×6」は → 「30×6=180」→ 「180−18=162」と視覚的に差し引き
- 「325+177」は → 「300+200=500、残り2と5を足す」などブロックで分ける
このような処理は、いわば“脳内ホワイトボード”を使っているようなもの。
いわゆるメモリーパレス(記憶の宮殿)の簡易版といえます。
そろばん経験者は“脳内そろばん”を持っている?
日本のそろばん学習者には、暗算力が非常に高い人が多いです。
これは、そろばんを長年使ってきた人が、頭の中に“見えないそろばん”をイメージするから。
実際、競技暗算の世界では、珠算(そろばん)の全国大会出場者が圧倒的に強い。
“パチパチ”という音はなくても、彼らの中では珠が動いているのです。
この「珠をはじく感覚」と「数値の動き」が脳で直結しているため、計算が“直感”に近くなると言われています。
計算を速くするための“思考のコツ”
暗算が得意な人の多くは、以下のような「頭の使い方」をしています。
分解して計算
例:48+27 →(50+25=75)−2=73
思い切って“近い数”に変換してしまう。
パターンで覚える
例:9×7=63 →「九九の裏ワザ」や「手のひらの指法」など
桁ごとに処理
例:372+148 →(300+100)+(70+40)+(2+8)
つまり、全体を一気に解こうとせず、小さく処理して積み上げているのです。
「計算が苦手」な人でも脳は鍛えられる!
ここまで読むと「自分には無理かも…」と思うかもしれませんが、心配無用です。
人間の脳には“可塑性(かそせい)”という特性があります。
つまり、「使えば使うほど伸びる」んです。
特に暗算は、以下のような方法で楽しく鍛えられます:
- 買い物で「合計いくら?」と頭の中で挑戦する
- 割り勘時に1人分をパッと出す習慣をつける
- 暗算アプリ・脳トレゲームでスキルアップ(例:Quick Brain, Math Master)
脳は筋肉と同じ。日々の“ちょっとした暗算”の積み重ねが、計算力に直結します。
まとめ:暗算力は「脳の使い方」で決まる!
暗算が得意な人の脳には、特別な才能が宿っている――
そう思いがちですが、実際はイメージ力・分解力・習慣の賜物です。
映像で数字を捉える人
珠をイメージで弾いている人
「まず10でまとめる」クセを持っている人
彼らはみな、脳の中で“数字との会話”をしているのです。
今日からできる暗算習慣、あなたも始めてみませんか?